|
2月15日
自分の言葉で語ろう!〜憲法と私たちの暮らし〜
9条改正は経済界の意志
吉野川市で「9条の会」を準備している山川・美郷の有志で、身近な人たちに呼びかけ、さくら診療所デイケア室でミニ学習会。おなじみ徳島大学の中嶋信教授がボランティア講義に来て下さった。テーマは「今なぜ改憲か?〜憲法と私たちの暮らし〜」

憲法改正、自主憲法制定は自民党結党来の目標だったが、今はむしろ経済界がそれを強く推しているという。(社)日本経団連の基本問題検討委員会(2005年1月)報告によると「内外の環境変化に伴い、憲法についてもほころびが目立ってきており、まずは現実との乖離が大きい第9条第2項(戦力不保持)と第96条(改正要件)の改正に着手する必要がある。」と明言している。たとえばトヨタには世界中に2万くらいの子会社があるようだし、経済のグローバル化に伴って海外で自国の軍隊に守られて安心(?)して経済活動が出来るようにとのことらしい。
人類史は「暴力支配の克服」に向かっている?
有事立法や国民保護法の成立でまるで戦前かと思うような今日この頃、何とも不思議で嬉しい中嶋先生のレジュメ。日清戦争時の国民の意思は「勝って賠償金を取る、これが国家発展の正しい道」と文化人のほとんどが日清戦争を「義戦」と思っていた。そしてその賠償金で日本は実際に産業革命を成し遂げる。ところが日露戦争の頃になると与謝野晶子の「君死に給ふ事なかれ」という有名な詩が現れ、日本人の意識も変わってきた。(日露戦争が事実上ロシアの国内事情で戦争が打ち切られたものだから賠償金が取れず、その不満が大正デモクラシーのきっかけとはなった。)その後、第2次大戦の大きな犠牲を経て国連憲章が制定される。
国連憲章第2条[原則](和訳)
3.すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並び正義を危くしないように解決しなければならない。
4.すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。(下略)
国連憲章には日本国憲法に通じるものがあり、世界191カ国が加盟しているのだ。
目指すべき方向は?
中嶋先生は経済の専門家らしく、日本社会を横軸:経済指数(市場原理まかせ→社会的管理)、縦軸:政治指数(政治的権威主義↑参加型民主主義)に表された。市場原理任せとはグローバリゼーションの進行を指し、今はまさにアメリカを中心に世界もそして日本も左側に動きつつある。右側は戦後日本が構築してきたさまざまな社会保障制度のある世界である。
いっぽう、政治的権威主義とは、進行している市町村合併やこれからの道州制のように国家管理がしやすい政治で、参加型民主主義とは、住民投票に象徴されるような「大事なことはできるだけみんなで決めよう!」という政治。
日本社会のベクトルは今左斜め下に向かっているが、私たちが目指すべき持続可能な社会は逆の右斜め上の方向。それがどんな社会か示せないために9月の総選挙で左斜め下を示せた自民が大勝した。具体的な夢を示すことが今こそ必要だ。
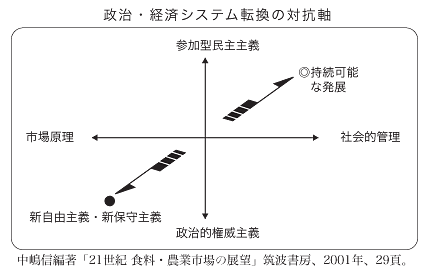
悲観的にばかりなってはいけない。南米では反アメリカの大統領が次々に誕生し、01年のブラジル世界フォーラムには世界のNGOが集い「もう一つの世界は可能だ!」と叫んだ。私にとっては98年に頑張って主催した(当時はホントに胃が痛かった。100名以上が参加してくれた。)地球市民教育フォーラムin徳島の記念講演で、池住義憲さんから初めて聞いた言葉だ。そして05年インドのムンバイでの世界フォーラムには14万人が参加した。WTOの提唱する「自由貿易の世界」は、途上国の主権を取りもどそうという草の根の運動で止まっている状態だ。
大きなスピーカーでがなり立てても人は理解してくれない。私たちが今どこにいて、世界の大きな歴史の流れの中でどうなろうとしているのか?客観的に見つめて、自分の言葉ですぐとなりの人に憲法を語っていく。身近な人に声掛けをする勇気こそが大切だということを、中嶋教授は静かに強く語ってくれたのだ。用意していた椅子は全て埋まり、アットホームな良い学習会だった。
|





